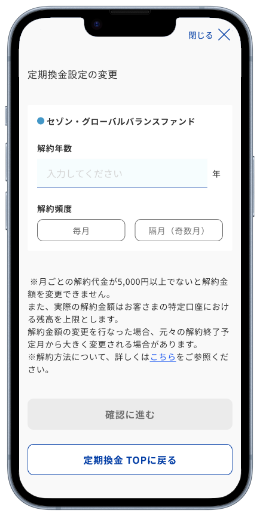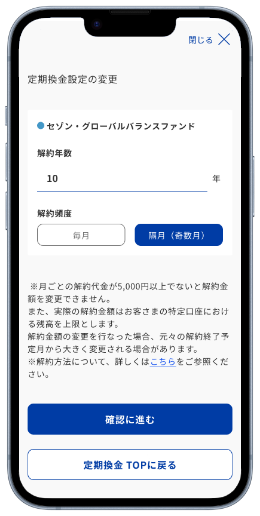定期積立プラン・定期換金サービス申込方法
-
定期積立プラン
申込方法 -
定期換金サービス
申込方法
申込方法
セゾン投信ネット取引で直接お手続きください。※画面はイメージです
-
①ホーム画面から「取引・積立」を選択

-
②ご希望のファンドを選択し、「定期つみたて申込」を選択
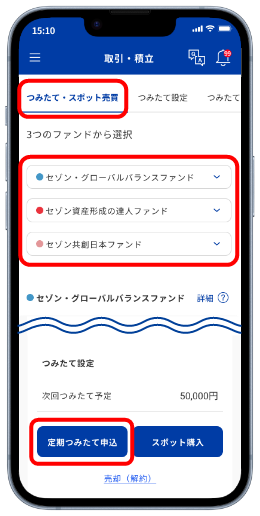
③引落口座の設定を行います。
口座振替またはクレジットカードを設定いただけます。併用も可能です。
※未成年のお客さまはクレジットカード設定はできません。
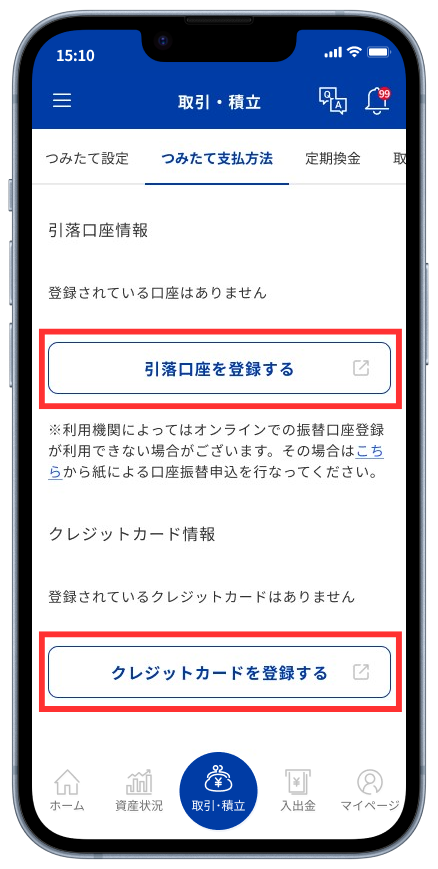
-
〈オンライン口座の場合〉
「オンライン口座登録へ進む」を押下し、ご利用される金融機関を選択してお手続きください。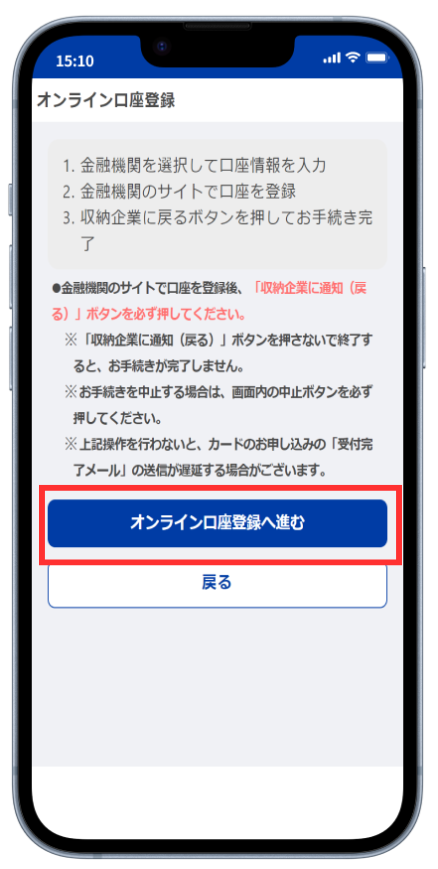
-
〈クレジットカードの場合〉
ご利用されるクレジットカードを選択してお手続きください。
④購入金額の設定
ファンドを購入する口座区分(NISA、課税口座)と購入代金の支払い方法を選択します。

毎月の購入金額や増額月の購入額を入力します。目論見書を閲覧していない場合は、目論見書の内容を確認します。

以上で設定完了です。

定期積立プランの支払い方法を変更する場合 ※画面はイメージです
口座振替からクレジットカード決済などつみたて設定を変更する場合、以下の手順で「変更したい積立設定を解除」のうえ、「引落口座またはクレジットカードのご登録と積立設定」が必要です。
①現在、設定中の積立設定の解除
取引・積立 ≫ つみたて設定 ≫ 支払い方法を変更したい申込と重複する設定中のつみたて契約を「解除」します。

②クレジットカードまたは引落口座の登録
マイページ ≫ つみたて支払い方法 ≫ 「引落口座を登録する」または「クレジットカードを登録する」を選択します。
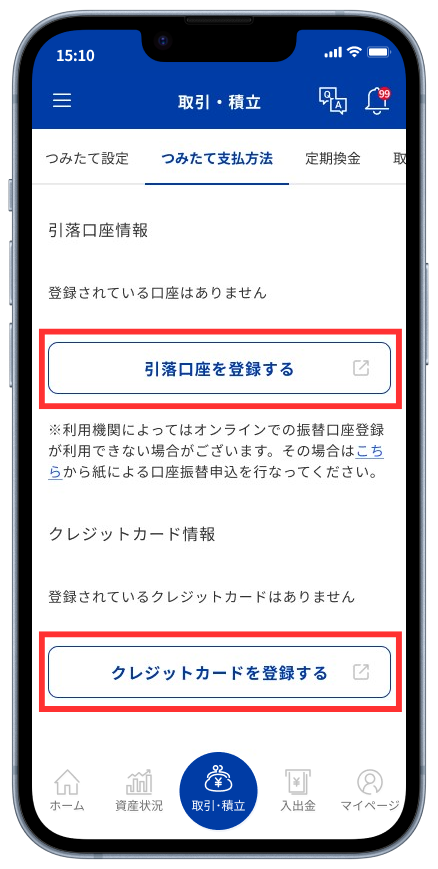
③希望するつみたて支払い方法で新規申込(口座振替・クレジットカード決済)
「定期つみたて申込」を選択します。

変更したい「支払方法」を選択します。

毎月の購入金額や増額月の購入額を入力します。目論見書を閲覧していない場合は、目論見書の内容を確認します。

以上で設定完了です。

申込方法
セゾン投信ネット取引で直接お手続きください。※画面はイメージです
-
①ホーム画面から「取引・積立」を選択

-
②「定期換金」タブを選択し「定期換金を申し込む」へ進む

-
③解約方法をご選択のうえ、画面の案内に沿って設定

変更方法
ライフステージに合わせて、期間、金額の変更のお手続きが可能です。
臨時収入等、定期換金が不要な場合は定期換金サービスは停止・解除も可能です。
①「定期換金」タブを選択し「定期換金設定を変更する」に進む

②画面の案内に沿って設定を変更
③停止や解除といった変更も可能

申込条件
対象口座:特定口座/NISA口座/一般口座
対象口座区分毎の1銘柄の評価額:申込時点において200万円以上
一回あたりの解約金額:1万円以上またはそれに相当する口数