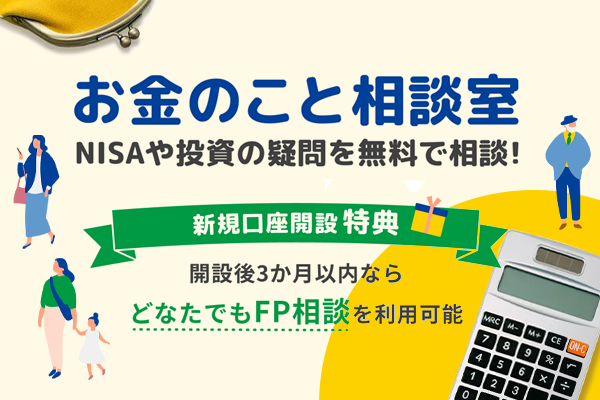年代別NISA活用法 50代編
公開日:
会社員であれば、そろそろ定年が視野に入る50代。一方で、子どもが独立し教育費の負担が徐々に減る時期でもあります。家庭のお金の流れに大きい変化が訪れる50代でも、資産形成の強い味方になるのがNISAです。
50代の人がNISAを使いこなすためのポイントをお伝えします。
目次
ポイント1 子どもの独立ごとに積立額をアップ
50代は子どもの大学の費用などで教育費負担が重くなりがちです。子どもが大学在学中は、無理をしない資産運用を心がけましょう。
50代での資産運用でも、活用したいのがNISAです。50代から始めたとしても、老後資産であれば10年以上運用期間が確保できるので、つみたて投資枠でコツコツと投信積立をするがおすすめです。
また、突発的な出費があっても、NISAの資金はいつでも引き出すことができます。資産運用に回したお金は使ってはいけないと思ってしまいがちですが、どうしてもという時は取り崩してOKです。それよりも、積み立てを継続することの方が大切。月2万円は運用資金を確保し、肩肘を張りすぎずにNISAに取り組んでみてください。
子どもが大学を卒業し、独立すれば家計に余裕ができるので、徐々に積立額をアップさせましょう。目安は、子どもが1人独立するごとに月2万~3万円の積み増しです。末子の大学卒業後、定年までは積立額の目標を夫婦で月8万円以上にすると、年間で100万円近くなりますから、まとまった資金づくりをしていけるでしょう。
ポイント2 老後資金の準備にはiDeCoも取り入れ、NISAと併用を
50代になると定年が視野に入り、老後資金についても具体的に考え始めなくてはいけません。
老後資金の準備に欠かせない制度に、iDeCo(個人型確定拠出年金)があります。iDeCoは、自分のための年金を自分で積み立てて運用していく制度。NISAと同様、運用で得た利益に税金がかかりません。それだけではなく、積立時や受け取り時にも税制優遇を受けられるのがメリットです。
NISAとiDeCoの比較
| NISA | iDeCo | |
|---|---|---|
| 18歳以上 | 対象年齢 | 20歳〜65歳未満 |
つみたて投資枠 120万円 成長投資枠 240万円 合計 360万円 | 年間投資額 年間拠出限度額 | 条件に応じて 24万円〜81万6000円(※) |
つみたて投資枠 投資信託 成長投資枠 投資信託、上場株式(国内外) | 運用商品 | 投資信託、定期預金、保険商品 |
| いつでもできる | 売却・資金受取 | 原則60歳以降 |
| 運用益(売却益、配当・分配金)が非課税 | 税制優遇 | 掛金は全額所得控除、運用益が非課税、受取時に所得控除 |
| 必要な時にお金を引き出せる安心感が欲しい人 | こんな人におすすめ | 老後資金を準備したい人 |
※2025年10月1日現在。2027年1月からiDeCoの年間拠出限度額が引き上げられる。
現時点で、運用益が非課税となる制度にはNISAと確定拠出年金があります。確定拠出年金は、老後の資産形成を目的とした年金制度で、企業型と個人型(=iDeCo)に分かれます。企業型は勤め先に制度がなければ加入できませんが、iDeCoは職業などによって条件は違いますが、誰でも加入可能です。50代で資産運用をする際は、NISAとiDeCoの両方を活用し、節税効果を最大限享受するとよいでしょう。
NISAとiDeCoの大きな違いのひとつに、資金の受け取り時期があります。NISAは運用中、お金が必要になったら保有資産をいつでも売却して現金化が可能です。一方、iDeCoは老後資金のための制度であるという特性上、原則として60歳までは資金の受け取りが認められていません。受け取り時期の自由度は低い代わりに、NISAよりも手厚い税制優遇を受けられるのが大きな魅力です。
iDeCoだけで資産運用をしてしまうと、急にお金が必要になった時にお金が引き出せないということになってしまいますから、両者のバランスをとりながらの併用が肝要です。毎月資産運用に回すお金の8割はNISA、2割はiDeCoで運用するなど、それぞれの家庭に合ったバランスを考えましょう。
なお、iDeCoの資金を受け取りできるのは原則として60歳以降ですが、60歳から受け取るためには10年以上の加入期間が必要です。50歳以降に積立を開始した場合には、受け取り開始時期も後ろ倒しになる点には注意しましょう。
iDeCoの受給開始年齢
| 加入年齢 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 50歳未満 | 60〜75歳 |
| 50歳~52歳未満 | 61〜75歳 |
| 52歳~54歳未満 | 62〜75歳 |
| 54歳~56歳未満 | 63〜75歳 |
| 56歳~58歳未満 | 64〜75歳 |
| 58歳~60歳未満 | 65〜75歳 |
| 60歳~64歳 | 加入5年経過後〜75歳 |
※65歳以降は掛金の拠出はできず、運用指図のみ可能。
ポイント3 徐々に安定運用に切り替え
50代ではどのような商品で運用すればいいのでしょうか。NISAとiDeCoのポートフォリオを考えてみます。
50代前半は、家計にあまり余裕がなくても、NISAのつみたて投資枠で月2万円、iDeCoは最低積立金額である月5,000円は積み立てたいものです。積立額が多くないのでリスクはあまり取らずに、世界各地の株式や債券などの資産に投資するバランス型投信をメインに運用を行います。ただ、資産を増やすことも考え、つみたて投資枠では25%の全世界株式型の投資信託も組み入れます。
50代前半のポートフォリオ(一例)
つみたて投資枠(月2万円)
全世界株式型25%バランス型投信
75%
iDeCo(月5,000円)
バランス型投信100%
50代後半になり、子どもが独立すれば積立額を増やしましょう。ここでは、NISAのつみたて投資枠で月6万円、成長投資枠で月2万円、iDeCoで月2万円を積み立てるとします。50代の資産運用の一番のポイントは、安定運用への切り替え。定年を控え、徐々に安定運用にシフトしたいので、基本的にはバランス型投信中心で運用します。
ただ、50代中盤以降に運用に回すお金を増やすことができたら、リスク資産への投資も検討してみましょう。一部、積極的に運用する株式型も組み入れるため、つみたて投資枠では引き続き全世界株式型の投信を25%、成長投資枠では今後成長の期待できる日本株式で運用する日本株式の投信を50%組み入れます。iDeCoでは、引き続きバランス型投信100%で運用を続けます。
50代後半のポートフォリオ(一例)
つみたて投資枠(月6万円)
成長投資枠(月2万円)
日本株投信50%バランス型投信
50%
iDeCo(月2万円)
バランス型投信100%
なお、NISAやiDeCoなどでの資産運用とは別に、生活防衛費として安全資産も確保しておく必要があります。これは、病気やケガなどで一時的に収入が途絶えたときや、車の買い替えや子どもの結婚式といった臨時のイベントがあったときなどに備えるもの。目安は、1カ月にかかる生活費の6カ月分です。月にかかる生活費が30万円なら、180万円が目標額です。
また、介護費用も徐々に準備が必要です。目安は夫婦で1,000万円(参照:年代別NISA活用法 60代編 コラム 夫婦2人で1,000万円程度は介護費に)。いきなり準備するのは難しいので、一部を退職金で準備し、足りない分は運用で準備するという選択をしてもよいでしょう。たとえば、今後受け取る退職金から500万円を確保し、残りの500万円はNISAの資産を徐々に売却して準備をするという方法もあります。売却後もNISAに残った資産は非課税で運用を続けましょう。
生活防衛費や介護費用は、必要になったときにすぐ引き出せることが大切。定期預金などの安全資産で準備しておきましょう。
コラム 子どもへの金融教育もNISAがおすすめ
NISAの口座開設ができるのは、国内に住んでいる18歳以上(※)の人です。条件を満たしていれば、高校生でも口座開設できます。
※口座開設年の1月1日時点で18歳以上。
そのため、NISAは子どもの投資デビューにもぴったり。たとえば、つみたて投資枠でアルバイトのお給料から月1万円で投資信託の積み立てにチャレンジしてもらったらどうでしょう。この先の運用期間が長く確保できる学生は、長期・積立・分散投資のリスク低減効果を得やすいのが魅力です。
親子で投資を始めて、どちらの運用成績がよいか競ったり、おすすめの投資信託を紹介し合ったりしても楽しいかもしれません。
\あわせて読みたい/
\お金やライフプランの相談窓口/
ライタープロフィール
酒井 富士子
経済ジャーナリスト/金融メディア専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。ファイナンシャル・プランナー
上智大学卒業。日経ホーム出版社(現日経BP社)にて「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長を歴任。リクルートの「赤すぐ」副編集長を経て、2003年から現職。「お金のことを誰よりもわかりやすく発信」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報を解説する。近著に『おひとりさまの終活準備BOOK』(三笠書房)、『お金の増やし方ぜんぶわかる!新NISA超活用術』(Gakken)など多数