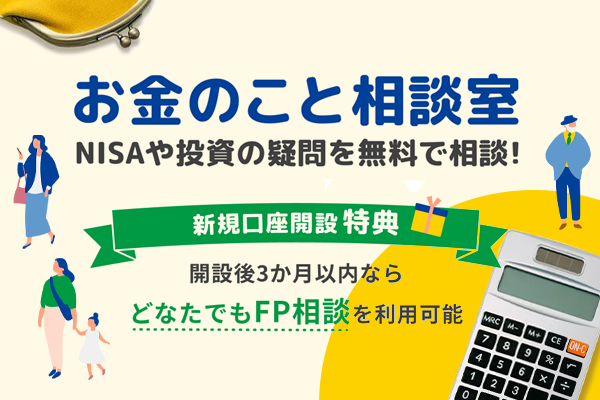年代別NISA活用法 30代編
公開日:
会社では中堅と呼ばれ、収入が上がり始める30代。一方で、子どもの教育費や住宅、車の購入など、ライフプランに伴う大きな支出が予測される年代でもあります。支出をカバーするための計画的な資産運用が欠かせません。
30代の人がNISAを使いこなすためのポイントをお伝えします。
目次
ポイント1 多忙な30代は「相場を読まない運用」を
2024年にNISA制度が新しくなり、投資による資産形成の重要性が広く認知されてきています。一方で、これから投資をしようと思っているけれど、どのような投資をすればいいのか、あるいは、実際に投資を始めたけれど、本当にこの方法でいいのかと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
そんな人にぜひ実践してほしいのが、「相場を読まない投資」です。これは「長期的に見れば、リスク資産の期待リターンは、預貯金を上回る」という前提に立ち、世界中の幅広い資産に投資する方法です。
一般的な投資では、購入する銘柄や売買のタイミングなどを自身で決めなくてはなりません。投資を始める前に知識を蓄えるための勉強も必要です。そもそも、一般的な会社員であれば、日中にチャートを眺めながら売買するデイトレーダーのような投資をするのは現実的ではありません。
特に、仕事での責任感も増し多忙な30代は、運用にかける時間も手間もそれほどかけられないことでしょう。「相場を読まない投資」は、そんな人にぴったりの投資術なのです。
成功のポイントは、「長期」「積立」「分散」の3つ。金融庁のデータでも、投資地域や投資資産を分散させ、あらかじめ決まった金額で長期的に積み立てていくことで元本割れのリスクを抑えられることが実証されています。
さらに、NISAを活用すれば、運用益(売却益、配当/分配金)も非課税です。運用商品や購入金額、購入頻度などを設定したら、あとは自動で定期的に買い付けが可能なため、手間もかかりません。税制優遇のあるNISAで経済成長の波に乗り、賢く資産形成を行いましょう。運用商品選びについては後述します。
ポイント2 「児童手当」は大学進学費用として貯めておく
子どもを持つ家庭にとって、大きな心配事のひとつが教育費でしょう。どのくらいの準備をしておけばいいのでしょうか。
進学先などにもよりますが、幼児期~中学時代はそれほど教育費がかかりません。高校時代も、最大年39万6000円が支給される支援制度(高等学校等就学支援金制度)があり、家計の負担は軽減されます。
ところが、大学生ともなるとそうはいきません。一気に教育費負担が重くなり、生活費でやりくりするのは難しいことが予想されます。
| 国立大学(※1) | 私立文系(※2) | 私立理系(※2) | 私立医歯系(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 入学料 | 28.2万円 | 22.4万円 | 23.5万円 | 107.7万 |
| 授業料 | 53.6万円 | 82.7万円 | 116.3万円 | 286.4万円 |
| 施設設備費 | - | 14.4万円 | 13.3万円 | 88.1万円 |
| 初年度合計 | 81.8万円 | 119.5万円 | 153.1万円 | 482.2万円 |
| 2年目以降 一年あたり合計(※3) | 53.6万円 | 97.1万円 | 129.6万円 | 374.5万円 |
| 4年間通った場合の総額(※4) | 242.6万円 | 410.8万円 | 541.9万円 | 2354.7万円 |
※1 「国公私立大学の授業料等の推移」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/content/20211224-mxt_sigakujo-000019681_4.pdf )をもとにセゾン投信作成
※2 「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員1人当たり)の調査結果について」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/content/20231226-mxt_sigakujo-000033159_1.pdf )をもとにセゾン投信作成
※3 授業料と施設設備費の合計
※4 入学料を1年分、授業料と施設設備費を4年分で計算。私立医歯系のみ入学料を1年分、授業料と施設設備費を6年分で計算
※ いずれも千円未満を四捨五入して表示
文部科学省のデータによると、入学初年度にかかる学校納付金の額は、国立大学で約81.8万円、私立文系で119.5万円、私立理系で153.1万円、私立医歯系で約482.2万円です。
2年目以降は入学金がかからないため少し負担は減ります。1年あたりの学校納付金は、国立大学で53.6万円、私立文系で97.1万円、私立理系で129.6万円、私立医歯系で約374.5万円です。
4年間通った場合の総額は、国立で240万円程度、私立文系や理系では400~500万円超。私立医歯系に6年間通った場合には2,300万円超にもなります。
総額で数百万円以上かかるうえ、一人暮らしや下宿をする場合には費用はさらに増すでしょう。事前の資金準備は必須といえます。
そこで、まず活用したいのが「児童手当」です。0歳~高校生年代(※5)の子どもを養育する人に対し、国から給付金が支給されます。
※5 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
支給月額は子どもの年齢によって変わり、3歳未満は1万5000円、3歳~高校生年代は1万円です。第3子以降(※6)なら、0歳~高校生年代まで一律3万円に増額されます。
※6 高校生年代までの子どもの数で計算。
この児童手当を使わずに貯蓄した場合、総額は230~240万円ほどになります(下記参照)。
3歳未満まで:54万円(1万5000円×12カ月×3年)
3歳~高校卒業:180万円(1万円×12カ月×15年)
⇒総額:234万円(※7)
※7 上記は第1子、第2子のケースで、3月1日~4月1日生まれの場合の例。4月2日~4月31日生まれの場合には、高校卒業までの期間が11カ月長くなるため、上記に11カ月分の児童手当11万円がプラスされ、総額245万円となり最も多くなる。
国立か私立か、どの学部に進学するかなどによって必要な金額は大きく変わりますが、仮に私立文系で自宅からの通学であれば、4年間の通学に必要な金額のおよそ半分を児童手当で賄うことができます。親が準備すべき費用は、不足分のみということになります。
さて、では不足分をどのように準備すればいいのでしょうか。必要な時期までに時間のある教育費は、NISAで準備するのも一考です。子どもが生まれてすぐに月1万円の積み立てを始めたのなら、18年間で元本216万円になります。運用の成果によっては積み立てた元本以上の資産形成ができる可能性もあります。もちろん、元本割れするおそれもあるので、預金でも支払うことができるようにしておくと安心です。
積立投資は、運用期間を少しでも長く確保した方が元本割れのリスクを軽減することができます。子どもを望んだときや妊娠中からでも、積立投資の検討を始めておくといいかもしれません。
ポイント3 ライフイベントに合わせて積立額を調整
30代は教育費、住宅や車の購入費用などで出費がかさむ時期。さらに、子どもが生まれるとフルタイムで働くことが難しく、収入が減ってしまうケースもあります。NISAでの積立額は、家計を圧迫しないように無理のない範囲で設定しましょう。途中で積み立ての継続が難しくなったら、減額しても問題ありません。大切なのは、少額でもいいから継続することです。
積み立てる資金は、使途に合わせて口座を振り分けましょう。まず、長期間かけて準備する資金は、NISAを利用するといいでしょう。具体的には、老後資産や子どもの大学進学費用などがそれにあたります。相場を読まない運用で、じっくりと資産を築いていきましょう。代表格は「全世界株式型」の投資信託を活用した運用です。長期的に積み立てることで、世界の経済成長と連動した資産形成が期待できます。ただし、株式および為替の変動を伴うため予めリスクを理解したうえで始める必要があります。
次に、短期~中期で必要となる資金は十分な運用期間を確保できないため、NISAの利用は考えものです。車や住宅購入の頭金など、数年以内に必要となる資金は、積立定期預金や個人向け国債などの安全な資産で準備する必要があります。
30代夫婦のポートフォリオ(一例)
つみたて投資枠(月2万円)
目的:老後資金
100%
積立定期預金(月2万円)
目的:住宅の頭金
つみたて投資枠(月1万円)
目的:大学進学費用
100%
積立額は、夫婦の働き方や収入、ライフプランなどに合わせて決めましょう。たとえば、上図のように夫婦で使途ごとに口座を分けて積み立てていくと、目標額までの達成度合いがわかりやすく管理しやすいでしょう。
NISAの運用資産の取り崩し方法には、主に「定額」「定口」「定率」の3種類があります。(参照:年代別NISA活用法 60代編 ポイント3 老後のために投資したお金をどう取り崩すかも考えておく)どの方法にも一長一短があるため、目的に応じた方法を選択することが大切です。老後資産の資金寿命を伸ばしたいのであれば「定率」がいいでしょうし、大学費用として資金の必要となる時期がはっきりしているのなら「定口」がいいでしょう。セゾン投信には、これら3つの解約方法を選べる「定期換金サービス」があります。一度設定するとその後は自動的に解約してくれるので、手間がかからず便利です。
なお、定期預金や個人向け国債などで積み立てている「短期~中期で必要となる資金」は、必要な時期が訪れるたびに取り崩すという方法で問題ありません。
コラム 成績確認のタイミングは?
積立投資は運用の手間がかからないといっても、完全にほったらかしはNG。次の3つのタイミングでチェックを行いましょう。
① 年に1回
家計全体の資産状況を把握するため、年1回は資産の「棚卸し」をしましょう。今の評価損益はいくらか、など、なんとなく把握するだけで問題ありません。多少運用成績が悪かったとしても、一喜一憂することなく、長期で積み立てを継続することでいずれは目標額を達成できるだろうというゆったりした気持ちでじっくり運用を続けましょう。
- 預貯金(普通預金、定期預金、財形貯蓄など)の残高
- 金融商品(NISA、iDeCo、株式などの有価証券)の評価額
- 貯蓄型保険(終身保険、学資保険など)の解約返戻金
実際に金額を書き出して一覧にしてみると、自分でも忘れていた口座の存在や資金の偏りなどに気づくかもしれません。冬休み期間中など時期を決めて、今後の資金計画を話し合う「家族マネー会議」を開催するのもおすすめです。
② 家計に変化があったとき
家計のお金の流れや資産額に変化があったときも、運用確認のタイミングです。たとえば、昇進して給料が上がったのなら、積立額を増やせるかもしれませんし、車の購入などで資金の取り崩しをするのであれば、その後の資金計画も調整が必要です。運用成績の確認とともに、積立額の見直しなどを行いましょう。
③ 市場に大きな変化があった時は敢えて成績を見ない
株価が暴落した時、大きな政治イベントがあった時など、自分の資産に影響があったのか、見てみたくなりますが、そういったタイミングでは敢えて見ないことです。長い運用期間の中では、大きく市場が下げることもありますが、いずれはまた上昇するものです。気にしないという意味でも敢えてみないという姿勢も大切です。
\あわせて読みたい/
\お金やライフプランの相談窓口/
ライタープロフィール
酒井 富士子
経済ジャーナリスト/金融メディア専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。ファイナンシャル・プランナー
上智大学卒業。日経ホーム出版社(現日経BP社)にて「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長を歴任。リクルートの「赤すぐ」副編集長を経て、2003年から現職。「お金のことを誰よりもわかりやすく発信」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報を解説する。近著に『おひとりさまの終活準備BOOK』(三笠書房)、『お金の増やし方ぜんぶわかる!新NISA超活用術』(Gakken)など多数